INDEX
少年中田くん
佐野 最初に中田さんのバックボーンについてうかがいたいと思います。中田さんは、動物行動学の専門家として、クモの性行動のひとつの研究結果を発表されています。それはNHKのEテレ『又吉直樹のヘウレーカ!』でも紹介され、私自身もクモの性淘汰という行動について知ることができ大変興味深く思いました。そのような生物学者に中田さんがなっていく前の、そして、北野高校に入学する前の、少年時代の中田さんについておうかがいいしたいと思います。中田さんはどんな少年だったのでしょうか?
中田 内向的な面があり、学者肌の少年でした。本当かウソかにこだわるタイプだったんです。世の中には、本当のことではない建前がいっぱいあるが、それに気づくと『違うじゃないか』と言って、トラブルになって困ることがありました。そういうことで、人間もいいのですけれども、住んでいた箕面が自然豊かなところで、家の敷地内を亀が歩いていたり、アリの行列がいたりして、そういった生き物を観ているのが好きな少年でした。ただ生き物が好きだといっても、昆虫採集して採集箱に珍しい虫を標本にして並べて他人に自慢するようなタイプでもなかったのです。外向的ではなかったので人に見せることもしなかった。誰にも見つからないところで、ひとりで生き物を観察するような少年でした。もちろん、普通に友達と遊んだりもしていましたが、一人で家にいるときは、庭にいる生き物を観るのが好きでした。
そして、中学生になって自分の将来を考え始めたときに、理科系の研究者になるのがいいなと思いました。当時は、まず天文学者がいいなと思っていたのです。宇宙の神秘を解きたいとロマンチックな考えを持っていました。しかし、当時の宇宙物理学や天文学の本を読んでみると、宇宙物理学というのは私たち人間の生活実感からあまりに離れたところで進められていたので、これはちょっと違うという感覚がありました。そこで小学生のころから生き物を観るのが好きだったから、生物学を学ぼうかな、と改めて考え直していましていました。

1967年大阪生まれ
京都大学理学部大学院博士課程満了
京都女子大学教授、学部長
動物行動学の専門家
「なんでも遺伝子を調べる時代に、
目に見える現象を扱うことにこだわる
ローテク研究者」
昼間も活動するカブトムシ
佐野 最近私が興味を持ったことがあります。埼玉県の小学6年生の柴田亮くんが、カブトムシは、シマトネリコという東南アジア原産、日本で庭木にもなっている木では昼間も活動していることを調べてわかったという話です。面白いと思ったのは、このカブトムシのことを調べるために、柴田くんが愛用していた昆虫図鑑を編集した山口大学理学部の児島渉先生に連絡を取って調べ方を聞いた。そうすると、研究のしかたを児島先生は教えてくれたそうです。カブトムシのお尻にマークを付けなさい、そしてその個体のカブトムシを見つけたら時間を記録しなさいと言う児島先生からのアドバイスによって、クヌギの木だと夜のみ活動しているカブトムシが、シマトネリコでは昼間も活動していることがわかった、ということです。柴田くんの“カブトムシ愛”もすごいけれども、調べ方を教えてあげた児島先生も素晴らしくて自分の成果にしようとなんて思っていない。そして、その後、二人で共著の論文を発表しています。なお、シマトネリコ原産の東南アジアの、シマトネリコに集まるカブトムシは、昼は活動しない、ということです。

1968年兵庫県生まれ
早稲田大学政経学部卒業
武田薬品工業で10年、DeNAで10年、
主にSEとして働く
「サラリーマン経験を経て
アラフィフから教会牧師に」
中田 これは、生き物というのはとても多様であることを示唆しています。同じ種類の生き物であったとしても、場所が違っていたり住環境が違っていたり、関係する他の生物の種類が違うと違う振る舞いをするのです。ですから、誰かがどこかで観たことは、他のところでは本当ではない、ということが起こります。そのため、学問という世界のなかで『権威者が育ちにくい』という特徴があります。私たちがやっているのは『マクロ生物学』と呼ぶのですが、実際に生きている生物を観察していく学問です。このマクロ生物学では『権威者が育ちにくい』ということが特徴としてあって、良い点でもあります。シマトネリコにくるカブトムシが昼も活動することを知った少年は、世界でだれよりもそのことに詳しくて、児島先生よりもその問題についてはすでにエキスパートになってしまっているわけです。
そして児島先生もそのことをよく理解されていらっしゃるから、そのように少年にアドバイスをすっとされたんだと思います。 私もいろんな研究をして論文を書いていますが、それはあくまでも私が観たところだけの話であり、他でも同じ事が起こっているかどうかは確認するまでわからないのです。
科学の再現性
佐野 科学ですら再現性がない場合があり、それは生物多様性だから、という中田さんのご説明でした。例えば量子論で、観察したら結果が変わるということと関連はあるでしょうか?
中田 量子論は、『観察するときに初めて状態が確定する』、ということです。一方、マクロ生物学でいう『多様性』とは、現象が極めて複雑なため、『再現性』が極めて取りにくいのです。
西洋科学というのは再現性に重きを置く分野ですが、同じ自然科学といっても物理学と生物学はずいぶん違います。物理学は再現性が高く斉一性が高いので、同じ現象がどこでも見られるという性質が強い学問です。すべてがいつでも当てはまるか、というとそうではないと思いますが、生物学よりはずっとその性質が強い。一方、生物学は、極めて複雑ですし、例えば私という人間が次の瞬間にどういう行動を起こすのか、私自身ですら予想できないわけです。そしてそのような主体が沢山集まって様々な現象を作っていくので極めて再現性が低いのです。そういう意味で、伝統的な自然科学である生物学は、物理中心主義の自然科学からは割と外れたところにあるのです。今日のテーマは理科系と文科系ということですが、理科系の一つの極北に物理学があるとすれば、ずいぶんと文科系側に寄っているのがマクロ生物学だと言うことができます。
生物学の学びの場としての京大理学部
佐野 中田さんが生物学を学ぶために、京都大学の理学部を選ばれた理由は何でしょうか?北野高校から京都大学に進学する学生が多いという事実は確かにありますが。
中田 マクロ生物学を学ぼうと思った時にどこがよいか、と考えた時に、そもそも東大は考えませんでした。高校生の時は、高校生のいきる世界の中だけで人生の将来予測をするじゃないですか。高校生の頃の移動範囲は、要は関西圏になるので、東京に行くなんてことは思いもつかなかったんです。そうすると、京都か神戸か大阪か、と考えた時に、その中で京都大学がマクロ生物学の学びがしっかりしている大学だった。そして、なぜ理学部かというと、私が学びたかったマクロ生物学というのは今日でもそうですが、お金を稼ぐことにはまったく役に立たない学問です。クモの繁殖行動を研究してもお金になりません。そういうことをするのであれば、理学部だった。で、実際、京大理学部は、今でも日本のマクロ生物学の中心です。
マクロ生物学の学びのなかで師匠は
佐野 マクロ生物学を学ぶ上での師匠はいらっしゃいましたでしょうか?
中田 大学で入った研究室は動物生態学でした。その研究室の教授が川那部浩哉さんでした。鮎の生態を調べておられて、すでに学会の超大物でいらっしゃいました。そのときに助教授としておられたのが安部琢哉さんです。このおふたりが動物生態学の研究室でご一緒させていただいた先生方です。その隣の研究室が動物行動学の研究室で、そこにおられたのが日高敏隆さんです。
師匠という意味だと自分が最初にはいった研究室で指導していただいた川那部浩哉さんと安部琢哉さんです。そのうち安部琢哉さんは研究中の事故で亡くなられました。それは、私が大学から初めて給料がもらえる形で仕事を始めたばかりの32歳のときに、長崎の私立大学に就職のために引っ越しをしました。その荷物が新居に入って佇んでいたときに、安部さんが事故でなくなったとの電話連絡が入ったのでよく覚えています。
マクロ生物学と進化論の関係
佐野 次に、マクロ生物学と進化論の関係についてうかがいたいと思います。中田さんが研究されていたクモの繁殖行動を観るときにそれは性淘汰だという話がありましたが、そうだとすると、動物行動学と進化論とは交流があるのではないか、と思われますがいかがでしょうか。
中田 もちろんそうです。動物の行動を研究するなら、すべて動物行動学の範疇ですが、対するアプローチというのはさまざまあって、例えばある行動を起こすメカニズムを調べるアプローチがあります。そのアプローチには例えば神経の繋がり方があります。目に光が入ってそれが視覚神経をとおして脳に伝わり、その結果として行動が生じるというのは、メカニズムの研究です。私自身は最初に生態学から生物学に入っているので、ある行動の生態学的な意味を考えることになります。生態学的な意味と行動を結び付けるアプローチです。
ある行動の生態学的な意味は何かというと、それはすなわち『数』の問題なのです。ある生き物がどのように増えるのか減るのか、あるいは地域によって多い少ないといった空間的な分布の問題として出てくるのは、やはり数の問題です。そして、この数の問題は進化の話と結びつくのです。正確に言いますと、進化のなかで『自然選択』と結びつくのです。
自然選択とは、要するに増えるか増えないかの話なのです。長い時間をかけて特定の遺伝的な性質が増えていくのか減っていくのかを問題にするのが自然選択です。
一方、生態学というのは遺伝的な性質は含まれますが、ある種あるいは個体群と言いますが、よく似た性質をもった集団が増えたり減ったりするのかに着目します。それが生態学のオリジンで基盤にある考え方だと理解してもらえるとよいです。
ではそのような観点から行動を観るとどうなるか、というと、生物のある行動がどのようにその生物の増える減るに繋がっているか、というのがひとつの筋です。
そのようなアプローチもありますし、さきほど例にあげた神経系や筋肉へのアプローチもありますし、心理学寄りのアプローチもあります。心の中をブラックボックス化して、心理学的に動物の行動にアプローチするのです。パブロフとかスキナーとか。そういう人たちもいます。
私自身は、生態学的なこともありますし、動物の心理や認知とか、そういうところにも片足をかけてやっています。
私がこの分野に入った時代は、動物の行動を研究をしている人たちの主流は、生態学のところから来ていて、その分野は『行動生態学』と呼ばれているんですけれども、行動生態学の全盛の時代でした。ですから私も研究するなかで、行動生態学がアクティブな時期でしたので、それと関係しますし、その考え方の枠組みを利用することもしています。しかし、私の根本的な疑問は、『生き物の気持ちを知りたい』ということです。
進化論をそのまま信じられるか
佐野 中田さんは自然選択、自然淘汰、性淘汰と言われるような言葉に表される進化論にある程度のっとりながら、生物行動学の研究をされていると理解しましたが、ダーウィンに始まる進化論をどのようにお考えでしょうか。進化論はマルサスの『人口論』にもヒントを得てダーウィンが思索を深めたと聞きます。そして『競争原理』という言葉が当てはまりそうな感じがしています。そして、それで説明できる部分もありますし、そうでない部分もありそうだと直観的に感じます。ですので、進化論をそのまま信じてよいのかという疑念を抱いてしまうのです。
中田 自然選択を競争原理という枠組みだけでとらえられるとしたら、それはちょっと偏っているというか、全体の凄く小さな部分のみを競争原理という言葉が指すだけだ、と。自然選択の理論が伝えていることは極めて単純で、『増えるものが増えていく』としか言っていないのです。では何が増えるかは、自然選択の大枠としての理論が関知するところではないのです。そして、その増えるものが増えていく、というのは言うならばトートロジーです。適応したものが適応する、生き残ったものが生き残る、というのと同じです。ですからこれ自体は反駁しようがありません。
であれば、そこは否定する必要がないので、大切なのは、では次のステップに進むことです。『どういう時に、どういう性質の生き物が増えるのか?』にダーウィン以降問いのレベルやフェーズが変わったのです。そのように考えると、競争に強いものが生き残るだけとは限らないということが明らかになります。
佐野さんに質問ですが、競争に強いとは、例えばどういうものを具体的に指しますか?
佐野 (少し考えて・・・)例えば、ネコ科の猛獣のなかで、ライオンのほうがチーターよりも競争が強そうに思います。チーターは走りが速いが顎が弱い。また、群れで狩りをしないので捕食が難しいのではないか。一方ライオンは強い顎を持ち、群れで狩りをして大きな草食動物も捕食することができるからです。
中田 その話は、状況を極めて狭い条件に固定したときにライオンの方が強いと言えるということです。さきほども言いましたように、場所が変われば、そして条件が変われば、全体の振る舞いは違ってきます。例えばある条件下で死にそうなシカがいたとして、そこにライオンの群れがきて、チーターが一匹きて、どっちがこの倒れそうなシカを食べるのかを観たときにライオンが勝ったとします。これをもってライオンのほうがチーターよりも競争能力が強くて生き残る。これが競争原理だとすると、それは『生物多様性』の観点とは異なるし、そぐわないのです。そのようなシチュエーションもありえるでしょう。けれど例えばそういう状況になったのが朝か夜か、死にそうなシカまでの距離が200メートルか50メートルかによって結果は違ってきます。競争で強いか弱いか、というのはそんな単純な話ではないのです。でもこの場合であっても、2つの肉食動物がいて、1つの餌を取りに行ってライオンが獲得し、チーターが獲得できずに飢え死にするならば、ライオンは子どもを残し増えていきます。もしこのチーターが最後の一頭だったら、チーターは絶滅することになるから、こうなればライオンは競争的に勝ったということもできるのだけど、でもライオンの競争能力が高かったと言って良いのか、というとそれはわかりません。たまたま状況がそうだった、ということもあります。
それでも、自然選択の原理自体は生き残っています。間違いようがないからです。ただ、どういう状況で何が生き残るかの説明を自然選択という理論はなにもいわない、ということです。
そこで、生物学者たちが寄ってたかって、こういう性質を持っているとこうではないか、と一生懸命調べているわけです。そして、そういう中で出て来たことが、結局、『生物は多様だよね』、ということです。そんな綺麗にユニバーサルに通用する「こっちが強い、こっちが弱い」という理論はないよね、という認識になります。自然選択の理論は私が思うところでは、突き詰めていくと、『生物多様性』の発見やその認識につながっていくことになったのです。そういう意味で、自然選択の理論は良い働きをしているのではないかと思います。
働かないアリに意義がある
佐野 なるほど!そして、『生物多様性』と言う言葉がなんども出てきました。そちらのほうにシフトしていきたいのですがその前にもう一度、自然選択について、文科系の素人から、理科系の専門家の中田さんにうかがいたいのですが、10年ぐらい前に、興味を持ったことがありました。
2011年に北海道大学の長谷川英祐先生が『働かないアリに意義がある』という本を出版されました。そこでは、働かない2割のアリがいるが、それを別にするとその中から働き出すアリが出てくるということを言っています。長谷川さんの結論は、アリが生き続けるために、2割の予備軍がいるのだ、例えば10年後に何かが起きて仲間がいっぱい殺されてもまだ働かないがまだ2割のアリがいるから、アリが生殖活動ができて全体として生き残るのだと言います。これは自然選択や進化論とは違うのではないかな、と思います。なぜなら、10年の間に何世代も変わっていくはずで、進化論ならばその瞬間瞬間に自然選択と自然淘汰の網にかかっているはずだからです。だから2割のアリを残すというのは進化論的な話ではないと私は思います。
長谷川さんはドーキンスの絶大なファンであることがわかりました。『利己的な遺伝子』のひとつだと説明しています。アリの原社会において、繁殖行動をするアリとそうでないアリがいて、そうでないアリのなかに働くアリと働かないアリがいて、働かないアリも全体の種の保存に貢献する利己的な遺伝子だと。利己的なことは結果的に利他的になる。それはなぜなら種が保存されたら自分の遺伝子が残るからだという説明です。ドーキンスの考え方で納得されていますが、進化論の考え方は超えているのではないかと私は思います。
ただ、反応閾値というのがあって、反応閾値の低いアリは働かない、しかし、他にいなくなったら、残った2割のなかでまだ反応閾値の高いものが動き出す、というのは非常にわかり易いと思いました。そうやって全体として2軍がいるようなチームになっているというのは理解できます。
中田 実は『働かないアリにも意義がある』に私も前半に少し登場しています。今でこそクモの研究をしていますが、大学院に入ったころはアリの社会学の研究をしていて、どのアリが働いてどのアリが働かないかの研究をして、それで博士号を取得しました。今でこそ、長谷川さんのほうが働かないアリ問題で有名になっていますが、90年代半ばはそれを日本で研究していたのは私だけでした。
動物を観察する動機のひとつは『人間を理解したい』ということでもあったのです。人間を理解するためには、人間と同じく『社会』をもっている生き物を理解しなければならないと考えました。働かないアリ問題も当時からありましたので。
その研究では一匹一匹のアリを麻酔して、指先で捕まえて細い爪楊枝の先に付けた絵具で色分けして、その一生を追いかけていました。一生とは半年間です。しかし、アリは次々に生まれてきますから、毎日毎日アリに色をつけていました。あるアリは今日30日歳になったからこういう仕事をしている、といったことを全部追跡していました。そのなかであまりアクティビティの高くないアリがいて、それだけ取り出すとどうなるか、といった実験をしたりまさにやっていました。
そして反応閾値モデルは当時からあって、集団のなかで働かないものを取り出して働くものがでてくるということを表すとてもきれいなモデルです。
そして、利己的な遺伝子の話はどういうことかというと、働きアリは自分の遺伝子を残すすべが自分自身にはありません。繁殖能力を失っているからです。アリも蜂もシロアリもそうですが、彼らの社会で働きアリ(働きバチ)が自分の持っている性質を残す唯一の方法は女王に子どもを残させることしかありません。女王とは自分の母親ですから、母親が子どもを残せば自分にとっては言えば兄弟姉妹で、家族です。家族を増やすことができれば、ドーキンスの言い方をすると、遺伝子を増やすという点ではOKなのです。
では今度ある瞬間働かないことが自分の家族を増やすことにどうして繋がるかということについてです。増える増えないということも大事な要素ですが、さらに大事なのは全滅しないということです。これは極めて大事です。ここで数がランダムに増えたり減ったりしている生物のことを考えてみてください。1万匹いるところで増えたり減ったりしている場合と10匹しかいなくて増えたり減ったりしている場合を比べてみると、10匹しかいないところで増えて減ってしていて、もしゼロになったら、そのあとはいなくなってしまいます。このような生物にとっては、絶対にゼロにならないということをする性質が現れたら、それをしない生き物よりも長期的に存続しやすいということになります。そして、リザーバーを残しておくというやりかたはゼロにならないための可能性を生む適応だと考えられます。リザーバーを残しておくことは短期的に不利になる、100パーセント働いていたほうがより沢山子どもが残せるのではないか、と考えがちです。しかし、長期的にみたら不測の事態が起きた時にゼロになる可能性を生むのであれば、短期的には損をしても長期的には絶滅しないやりかたを採らないと生き残らないのです。ですから、今生き残っている生き物のなかで短期的には効率的ではないような生き物がいてもそれは不思議ではないのです。
この話はさきほどの話と同じで、何が生き残りに寄与するのか、と私たちが考えるときに、短期的なことだけではいけない、長期的なことも考えなければならないということです。この短期的な不利と長期的に生き残る両軸のバランスを取ることができたものが生き残る。ということは進化論とは矛盾しない、ということになります。
佐野 なるほど!短期と長期の時間軸で観る大切さが少しだけイメージできました。しかしとにかく、ドーキンスの利己的遺伝子の説明能力の強さを感じます。
中田 なんでも説明できます。さきほども申しましたように、自然選択の理論に反論するのは不可能です。そもそも『神が生き物を造った』という話へのアンチテーゼとして出てきていますから、それは間違いようのない理論であっても構わない。そこを『それは違う』とか『間違っている』といっても生産的ではありません。それよりも、『ではどういう時に?』と考えていくと、そうするとこれは『多様性』の問題になっていくわけです。
(前編終り)

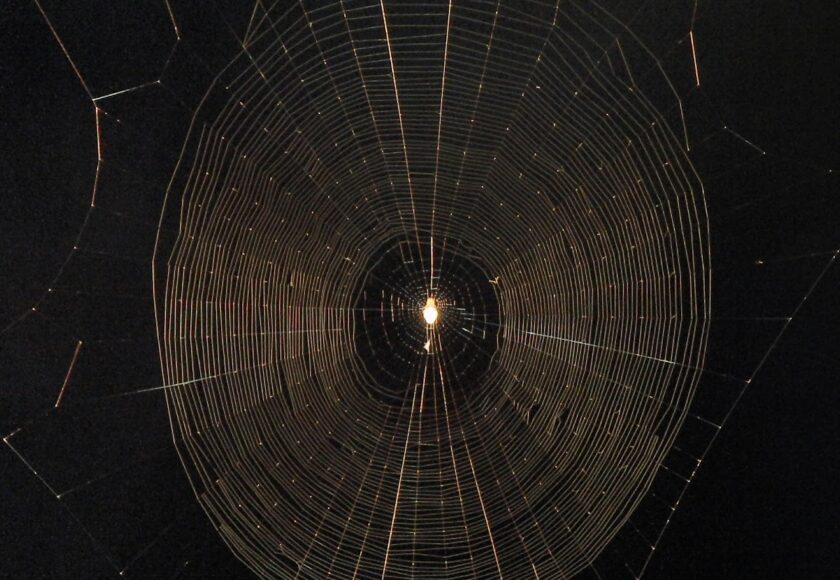


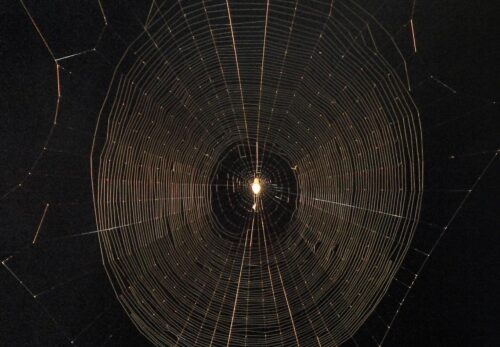



この記事へのコメントはありません。